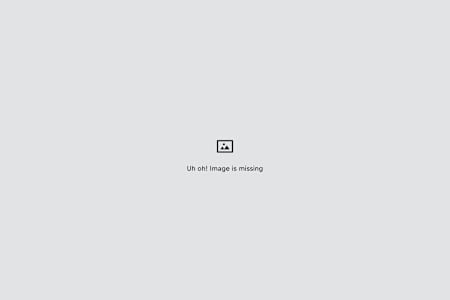パイドパイパーハウスは情報交換の場所だった
――パイドパイパーハウスはいつ頃からいつ頃まで営業していたんでしょうか。
75年の11月から89年の6月29日ですね。
当時はまだ輸入盤の専門店はそれほど多くなかったですね。原宿にはメロディハウスがあったし、神田や西新宿にもレコード店があった。ディスクロードやディスクユニオンのようなチェーン店もあった。けれど、個性のある小さな店が多かったんですよ。
しかし81年に渋谷の宇田川町にタワーレコード渋谷店がオープンしたあたりから徐々に大きな輸入レコード店が増えていった。
――当時の小さなレコード店たちは音楽好きの集まるサロンのような場所だったんでしょうか。
そうですね。ただ、パイドパイパーハウスは特殊だったと思います。開店当初から数年間はカフェスペースがあって、輸入盤と国内盤のレコードだけじゃなく、音楽雑誌やミニコミ、ソングブックも取り扱っていました。
店に立つようになる前から音楽の仕事はしていたのですが、よくパイドパイパーハウスのカフェスペースで打ち合わせをしてました。細野晴臣さんや吉田美奈子さんとの待ち合わせに使ったり。
――以前にオリジナル・ラブの田島貴男さんにインタビューさせていただく機会があったんですが、当時のパイドパイパーハウスを「いろんなレコードを聴いたり、いろんな音楽を教えてもらう先輩が沢山いる場所だった」と仰っていました。そうやって出会いを作る役割がとても大きかったんですね。
そうですね。ベテランのミュージシャンから、ギターを抱えた音楽家を目指す若者まで、いろんな音楽好きの人たちが入れ替わり立ち代わり来ていました。小西(康陽)君もそうでした。彼が「聞いてください」と店に持ってきたデモテープがピチカート・ファイブのデビューのきっかけになったり。そういうことが店頭で起こっていました。
ただレコードを並べて売るだけではなく、こちらも良い音楽を紹介する。通ってくる人達からも情報をもらう。そういう情報交換の場所でもあったわけです。
MTVの時代になった
――80年代に入って、渋谷の宇田川町にレコードショップが徐々に増えていったことについてはどう見ていましたか。
やっぱりタワーレコードがオープンした時には「これは脅威になるかな」と思いました。あれだけの売り場面積があって、従業員も何十人もいて、値段も安いし、ディスプレイも派手だった。僕らは多くても2人ですからね。ただ、渋谷店の初代店長と付き合いがあったので、お互いに情報交換をすることもありました。
ーーーーーー
オープン当時(1981年)のタワーレコード
その後“渋谷の音楽”の象徴的なエリアのひとつになっていく「宇田川町のレコード街」の一角に、輸入版の専門店としてタワーレコード渋谷店はオープンした。
国内における大型輸入レコード店の先駆けとして日本進出、オープン当時は音楽業界に衝撃が走った。そして音楽ファンたちが最新の洋楽に触れるための環境も変化していく。
ーーーーーー
――80年代の音楽業界はどう変わっていったんでしょうか。
タワーレコードなどのような大型輸入レコード店が増えていくのと当時に、テレビでMTVが放映されるようになった。そこはリンクしていたと思います。新しい欧米のヒット曲のMVがテレビで流れて、それが流れた頃にはもう店頭でレコードが買えるという。
僕が少年時代を過ごした60年代にはそういうことはあり得なかった。アメリカでヒットした音楽が日本で聴けるようになるのは早くて3ヶ月後でした。
――MTVがスタートしたのは81年。80年代中盤には地上波でも番組が放送されて、マイケル・ジャクソンなどのアメリカのヒット曲がそのまま日本のお茶の間に届いていた時代でした。
僕は長崎が地元だったので、それまでもFEN(米軍極東放送網。1945年から在日米軍向けに放送されていたラジオ局)でリアルタイムでアメリカのヒットソングを聴いていましたが、そういうことができるのは限られた人でした。下手したら日本ではレコードが手に入らないこともありました。
―― 60年代や70年代のアメリカのポップスは限られた人だけがアクセスできるものだったわけですね。しかし80年代、MTVと大型輸入レコード店ができたことで、それが大衆化した。
そうですね。ただ、パイドパイパーハウスはそうじゃないところに行こうとしました。 それこそマイケルとかマドンナとか、そういったものはどの店にも大量に置いてあるわけですね。パイドでも初回はある程度並べるのですが、品切れになっても必死で補充することはしませんでした。
値段も大型店には適いませんし、それよりも僕らが好きな音楽、たとえばヴァン・ダイク・パークスとか、ドクター・ジョンとか、ローラ・ニーロとか、ジョニ・ミッチェルとか、ホーギー・カーマイケルとか、そういうものの在庫を切らさないようにしていました。
――当時のパイドパイパーハウスはマニアックな場所だったと思いますか?
両面があったと思います。店に入って正面には売れ線のものも並べてある。ただ、一段奥に行くと別世界なんですね。そこに“趣味趣味音楽”というコーナーがあって、ほとんどラジオやテレビで流れないものを置いていた。
でも、店でそれをかけていると「これ、なんですか?」と聞いて買っていくお客さんがいるんです。高校生のような若い子でもそういう人がいましたね。
渋谷系のルーツは何か
――80年代中盤は、アメリカのヒット曲がMTVで日本に届く一方、イギリスでさまざまなインディーレーベルが勃興する時代だったと思います。
僕らはむしろそっちの方をプッシュしていましたね。80年代のイギリスからはニューウェーブやネオアコが出てきて、「やっと出てきたな」という感じでした。音楽もお洒落だし、アートワークやデザインもレトロな感じだけど新鮮さがある。小西くんや信藤(三雄)さん、橋本徹くんもそのあたりに注目していました。
――そういったインディーポップを愛好する音楽好きが、渋谷に集っていたような実感はありましたか。
ありましたね。 ちょっと遠回りしてパイドパイパーハウスによってみんな渋谷に集まるみたいな感じでした。
あとは桑原茂一くんがやっていた原宿のピテカントロプスとかにもよく行っていた。世代は少し違うんですけれど、茂一くんや、藤原ヒロシくん、橋本徹くん、小西康陽くん、インク・スティックの松山勲さんたちはみんな同じ時期にパイドパイパーハウスに来てましたね。
――90年代にかけての時代の変化についてはどう見ていましたか?
僕はパイドパイパーハウスをやりつつ会社を作って、海外のアーティストのコンサートを主催していたんです。で、よく覚えていることがあるんですけれど、89年にやったダン・ヒックスのコンサートに、小西くんや、フリッパーズ・ギターの二人や、ロッテンハッツや、その後90年代に活躍する若いミュージシャンたちが、みんな客席にいたんです。
――当時はまだデビュー前の人も多かったですよね。
そうですね。パイドパイパーハウスが閉店する日の夜に田島(貴男)くんがギターを抱えて「夜をぶっとばせ」を歌ってくれた時のことも鮮明に覚えてますね。店内にあった木の切り株のスツールの上で、ギターをかき鳴らしていた。彼も含めて、ダン・ヒックスやフィービ・スノウを観に来ていた若者たちが活躍していくようになって、いつの間にか、その辺の人たちを指して「渋谷系」と呼ぶ動きが出てくるようになったんです。
――80年代のパイドパイパーハウスから90年代の渋谷系は地続きでつながっているわけですね。
そうかもしれませんね。ピチカート・ファイヴが海外に進出してからは、海外のメディアからそういう取材を受けたこともありました。
タワーレコード渋谷店は天国のような場所
―― 改めて80年代の渋谷と音楽を振り返って、どういう時代だったと捉えていますか?
やっぱりレコード・ショップ、CDショップが沢山できた時代でしたね。渋谷に行けば事足りるようになった。
これは海外のアーティストにとってもそうです。僕が招聘して来日したミュージシャンが「レコードを探したいからホテルは渋谷にしてくれ」と言うようなこともあった。
世界的にもあんなにレコード・ショップが何十軒も並んでいる街はなかったんです。
あと、その後90年代になると、バート・バカラックやA&Mサウンズのような、日本で言うソフト・ロック、海外で言うイージー・リスニングの人気が出てくるんですが、大胆に言えば、その大元になったのは80年代に出た一枚のレコードだったのかもしれない。
――というと?
87年に日本だけで出たロジャー・ニコルス&スモール・サークル・オブ・フレンズのCD再発がなかったら、ひょっとしたら違っていたかもしれないと思うこともありますね。68年に出て、その後廃盤になっていたんですが、パイドパイパーハウスではカット盤を1000円前後で売っていて、それをミュージシャンや音楽関係者達がみんな買っていました。アメリカ本国でもヨーロッパでも全く知られていなかった一枚のレコードが再発されて、その嗜好や音楽性が、渋谷系のムーブメントを経て海外のマニアにも注目されるようになった。
―― 過去の名盤を新しい感性で蘇らせる。そういう感性が渋谷系の基盤になったということでしょうか。
ソフトロックだけじゃなく、モンドやラウンジ・ミュージックもありました。イタリアの映画音楽のようなマニアックな音源も若い人たちの間で聴かれた。そういう音楽を愛好する人たちが渋谷に点在するレコード屋に通っていたわけですね。
――そう考えると、若い人が昔の音楽を掘り返すようなムーブメントこそ、80年代に生まれたカルチャーだったと言えるかもしれません。
そうですね。それが渋谷系の源流になったのかもしれない。大学生をはじめ、音楽家の卵たちが渋谷の中古盤店やタワー・レコードにリイシュー・コーナー目当てに通っていた時代でした。当時、来日したアメリカのミュージシャンを連れて、渋谷のタワーに行ったんですが、再発盤やイージー・リスニングのコーナーに若者がたくさんいて驚いてました。アメリカだと昔を懐かしむ年寄りばかりなのに、って。
――そういった趣向性は一時のブームではなく今も定着していると思いますか?
そうですね。今もそれは続いています。去年からはタワーレコード渋谷店の中でパイドパイパーハウスをやっているので、店にいるとわかるんです。
若い女の子がアナログを熱心に見て買っていく。それに、毎日数十人の海外のお客さんがやってくるんです。そういう人たちが沢山のアナログレコードやカセット、日本でしか出ていない再発CDを買っていく。
洋楽だけでなく、はっぴいえんど、ピチカート・ファイヴ、山下達郎、坂本龍一のような日本の音楽も買っていく。タワーレコード渋谷店は天国のような場所なんでしょうね。いろんな国の言葉が飛び交っていますよ。